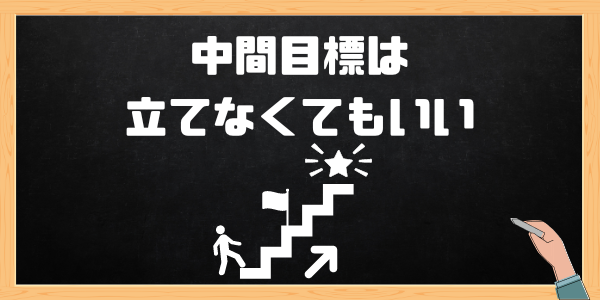叶えたい目標はありますか?
叶えたい夢はありますか?
いまこのブログを読んでくれたあなたは、きっと夢や目標に向かって歩んでいるのだと思います。
目標を決めるやり方はいろいろとあるんです。
その1つに「中間目標を細かく立てる」というものがあります。
結論から申し上げると、中間目標を立てることはメリットもデメリットもあるということをお伝えします。
理由も含めて説明していきます。
中間目標のイメージ
中間目標を立てるというのはどういうことか。
登山に例えてみましょう。
お昼ご飯を頂上で食べるため、「12時までに頂上に登る」という目標を立てたとします。
中間目標とは「10時までに5合目に登る」という文字通り中間の目標を立てることです。
ときには「3合目に9時、8号目に11時」という具合にとにかく細かく設定する場合もあります。

細かく中間目標を決めることで、メリットとデメリットが生じるのです。
中間目標のメリットとデメリット
中間目標を置くことのメリットは、定期的に決めた目標を達成できているかどうかを確認できることです。
ゴールまでの道筋がしっかり見えていて、それを達成させるための中間目標が見えている場合、達成することで自信につながります。
デメリットがないように思える中間目標。
では、もしその中間目標が叶わなかったらどうなりますか?
例えば先ほどの登山の例。
10時までに5合目にたどり着くと目標を立てたのにもかかわらず、登山道が混雑して10時を過ぎたとします。
この時、「挽回できるから大丈夫」と思える人もいれば「やばい、もう無理だ。間に合わない…」と思う人もいます。
後者の場合、自己効力感(後述)が下がってしまい、最終的に叶えたい目標が叶わなくなってしまう可能性があるのです。
余談ですが、わたしは過去に一度だけ富士山に登ったことがあります。
頂上でご来光を見るために夜9時ごろから登り始めましたが、当時は富士山ブームで大混雑。
もう少し遅ければ日の出に間に合わなくなるほど時間がかかったことを覚えています。

自己効力感とは?
「自己肯定感(Self-esteem)」という言葉は聞いたことある方も多いのではないでしょうか。
自己肯定感を簡単に説明すると、ありのままの自分を受け入れる・自分を肯定する、ということです。
「自己効力感(Self-efficacy)」はスタンフォード大学の心理学教授、アルバート・バンデューラによって提唱された考えです。
目標を達成できるという可能性を認知しているという感覚、いわゆる「やればできる」という感覚です
目標を達成するために意識してほしいのは、自己肯定感よりも自己効力感と私は考えています。
それはなぜか。
もう少しお付き合いくださいね。
人生は予測できないことの繰り返し
先ほどの登山の例のように、不測の事態というのは必ず起きます。
(わたしの場合、混雑くらいは予測できたかもしれませんが笑)
同じくスタンフォード大学の教授、ジョン・D・クランボルツはこう言いました。
キャリアの8割は予想しない偶発的なことによって決定される
ジョン・D・クランボルツ 計画的偶発性理論
みなさんの人生を振り返ってみても、計画通りに進んできた事例はばかりではないでしょう。
人生は予期しないことの繰り返しなのです。
もし最初から中間目標を細かく決めて、やるべきことを絞ってしまったら、どうなるでしょうか。
それが叶わなかったらどうなるでしょうか。
自己効力感が下がってしまい、「やるぞ!」っていう気持ちが下がってしまわないでしょうか。
だからこそ、中間目標に拘り過ぎなくていいのです。
最終的に叶えたい目標を常にイメージし、そこに向かって一歩ずつ歩んでいくのです。
ちなみにまた余談ですが、富士山には登山道が大きく分けて4つあります。
道は1つとは限らないのです。
中間目標に拘らず、様々な可能性を受け入れることができたら、あなたの成長の幅はきっと広がります!
登山は誰かと登ろう!
一人で目標に向かって登っていませんか?
誰かに相談したい、目標を達成するために誰かに支えてほしい。
そう思ったら、スポーツメンタルコーチはいつでも話を聴きます。
1時間のセッションを体験(有料)することもできますので、興味がある方はいつでもご連絡ください。