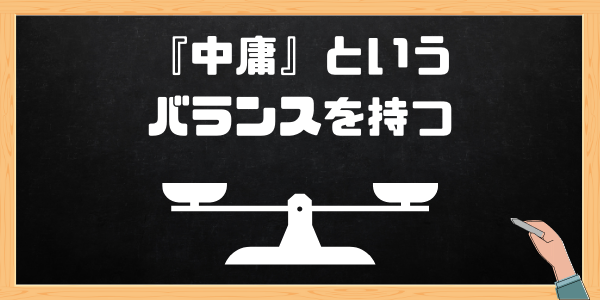『中庸(ちゅうよう)』という言葉をご存じですか?
簡単に言うと、極端になり過ぎず、偏らないことです。
頭ではなんとなく分かっていても、なにかを考える時に極端な考えに偏ってしまうことがありますよね。
例えば、ダイエットをしている人が「糖質や脂質を一切摂らない!」という考えはどうでしょうか。
一つの考え方なのでもちろん否定はしませんが、「一切摂らない」というのは極端ですよね。
生活していくうえで最低限の糖質や脂質は必要です。
「ダイエット=なにかを完全に断つこと」というよりも、「そういうやり方もある」という広い考えを持つことが、心を整える一つのポイントなのです。
中庸の考え方を学んで広い視野と考え方を持ち、スポーツにも活かしていきましょう!
中庸とは
『中庸』という言葉は、古代ギリシャの哲学者・アリストテレスや、「論語」で有名な孔子の言葉からきています。
【中庸(ちゅうよう)】
1、偏ることがなく、バランスがとれていること
2、過大でも過少でもなく、徳の中心となる概念
中庸とは、偏り過ぎず・多過ぎず・少なすぎず、という考え(もしくは心のあり方)です。
自分でも気づかずに偏った考えになることもあります。
その結果、思い込みが強くなることにもつながるのです。
偏った考えになるのではなく、常に中庸の考え方を意識していきましょう。
中庸であることは双方を知ること
では、「中庸」とはなにを意識すればいいのか。
中庸を意識するためには、「物事の逆」をイメージすることです。
わかりやすい例ですと、極限までお腹がすいた状態と、超満腹な状態。
食事制限をしてお腹がすいた状態は体に何かしらの影響が出ますし、食べ過ぎが良くないのもイメージできるでしょう。
「腹八分目」という言葉もある通り、適度な食事が一番ということですね。
また、食事の例でもう一つ書くと、世界各国の食事情も一例です。
2022年5月現在、日本は食料品の値上げが話題になっています。
一方で、満足にご飯が食べられない国もあるのはみなさんもご存じでしょう。
食べるものがたくさんある国もあれば、そうではない国もある。
双方をイメージすることで、中庸の考えを意識することができます。
いろんな考えがあるということを理解する
地球規模で見た場合、北極点と南極点があり、その真ん中に赤道があります。
北から南の間のどこかにわたしたちは暮らしていますよね。
それぞれに暮らしている理由があり、それぞれの考え方があります。
みんなが北極点にいるわけではなく、みんなが赤道直下にいるわけでもありません。
中庸でいるというのは、シーソーのようなもの。

写真のような4人乗れるシーソー。
どこかに誰かが乗れば、シーソーは偏ります。
誰かが動けば、シーソーは揺れます
でもそこには常に「真ん中」があります。
写真の例で例えれば、赤いバネの部分さえしっかりしていれば、ブレることはないのです。
真ん中があるから両端がある
両端があるから真ん中がある
様々な考えがあるということを理解した上で、常に「真ん中」を意識することが心のブレを抑えるコツです。
「あ、こういう考え方もあるのね」
という具合に受け止めてみましょう。
中庸でいることでコミュニケーションが良くなる
チームや部活など、組織でスポーツをしている人は多いでしょう。
広い意味で捉えれば、たった一人でプレーできる人はいません。
組織の中で、コミュニケーションが大切であることは言うまでもありませんよね。
だからこそ、自分自身が『中庸』の考えを持つのです。
自分とは違う意見があった時に反発するのではなく、1つの意見として受け入れる
自分の意見=正解、と思い込まない
中庸の徳たるや、其れ至れるかな。
孔子『論語』
孔子が『論語』の中で説いた一文です。
「中庸でいることの徳には至上の価値がある」と言っています。
古い書物にも、スポーツメンタルのヒントはあるのです。
「何事にも中庸でいること」
決して簡単ではないかもしれません。
わたしも日々学んでいます。
中庸を知り、中庸を意識する。
得られた徳は、かならずあなたのチカラになると信じています!